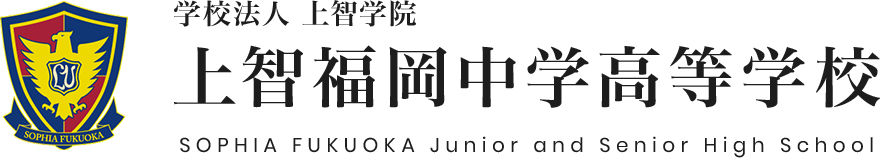4月7日(月)に中学2年生~高校3年生の新年度始業式、4月8日(火)に新中学1年生の入学式が行われました。本年度の学校目標は「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人に」。このテーマをもとに学校長から生徒に話がありました。以下、終業式、入学式の学校長訓辞です。
【始業式訓辞】
皆さん、おはようございます。桜も満開となり今日から新たな学年が始まります。希望にあふれる手つかずのこの一年を始めるにあたり、昨年度生活面学習面でうまくいかなかったところは改善し、うまくいったところはより伸ばして、この一年素晴らしい成長ができるように頑張ってまいりましょう。もちろん私たちは皆さんの一年の歩みを全面的に支援し、協力します。
ところで、昨年度は「息をするが如く隣人になれ」を目標に、隣人愛についての理解を深めてきました。人を線引きせず誰に対しても吐く息のように自分から友達になる。友として利益や見返りを求めず自分がしてほしいことを相手にしてあげる。皆さんも経験があると思いますが、このように誰かのために一肌脱いだ時、たとえ感謝されなくても本当の幸せを感じます。これが隣人愛です。
去年はさらに、それにとどまらない隣人愛の奥深さも知りました。私たちには誰しも馬が合わない人、理解できない人がいて、えてしてその人を無視したり、怒りや苛立ちをぶつけがちですが、それを今度は息を吸うようにグッとこらえて、欠けたところだらけの私たちを慈しみ深い神様が忍耐をもって受け止められているように、私たちもその人を忍耐をもって受け止める。これこそ、より深い隣人愛だと知りました。
これを踏まえて、今年度皆さんが隣人愛を一層深め、誰に対しても友となることを勧めます。そのため今年の学校目標は「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人に」とします。というのも、これは自分が本当に友として人を愛せているかどうかがよくわかる言葉だからです。
例えば、目の前に喜んでいる人がいるとしましょう。私たちがその人に「すごいね、よかったね。」と言って一緒に喜んでいたならば私たちは間違いなくその人の友です。しかし、「チェ」と舌打ちして喜ぶ人を妬んだり、不愉快に思っていたならば友と言えるでしょうか。ましてや、その人の喜びに無関心であるなら友とは言えません。愛の反対は無関心だからです。
同様に、目の前に悲しみやくやしさで涙を流している人がいるとしましょう。私たちがその人の辛さを我がことように感じて心を痛めたり、ともに涙を流していたならば私たちはその人の友です。しかし、こんなこともあるかもしれませんね。実は私たちがその人を傷つけ泣かせていたり、その涙を見て「ざまあみろ」と嘲笑っていることが。あるいは目の前に悲しんでいる人がいるのに無関心で何も感じないならどうでしょう。いずれも友ではありません。このように自分が友として人を愛しているかどうかがこの言葉からわかるのです。そして、ここからが大事な点です。喜びも悲しみも互いに分かち合える友が増えれば増えるほど私たちは幸せであり、逆に自分の喜びを喜んでもらえない。自分の悲しみをわかってもらえない。それどころか傷口に塩を塗るような人がいる。この時は、私たちだけでなく、その塩を塗る人さえも心に平安がなく、誰も幸せではありません。
「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人に」これはパウロのローマの信徒への手紙から頂きました。そこには次のように書かれています。「愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。(中略) 喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。」(ロマ12.9-15)まずは今日初めて集うクラスメイトから、お互い相手を優れたものと思い尊敬をもって接し、喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣くことができる友になりましょう。この一年の皆さんの上智福岡生らしい成長を心から願って、これを始業式に当たっての言葉といたします。この一年頑張ってまいりましょう。
【入学式訓辞】
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今日から皆さんは上智福岡中学高等学校第82期生です。皆さんの母校となる上智福岡は、「自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。」と言われるイエス・キリストの隣人愛に基づき、一人ひとりが神様から頂いたタレントを他者のためにも生かし、他者とともに幸せな人生を生きる人を育てる学校です。そしてその成長に欠かせないのが同級生としてここに集う146名の仲間です。この仲間がいてくれて、6年間ここで仲良く生活する中で、時にはぶつかり傷つけあい、再び仲直りするからこそ、皆さんは徐々に自分を愛するように隣人を愛することができるようになります。そんな仲間が今日できたことを心から喜んでください。
また、ご列席のお父様、お母様、お子様のご入学を心よりお慶び申し上げます。私たちは皆様と手を携え、これからの6年間、分け隔てなくお子様一人ひとりの成長を全面的に支援し協力いたします。お預かりするお子様はまだ成長の途上ですから、もしかしたら、お子様が友達を傷つける、あるいは友達に傷つけられることがあるやもしれません。しかし思えば私たちも幼いころ多くの過ちを赦され、ようやく大人になれました。お父様、お母様には我が子を愛するように、ここにいる146名の子たちを大きな愛と温かい眼差しで見守っていただき、ともに82期生を育てていただけたら幸いです。ご協力をよろしくお願い申し上げます。
さて、82期の皆さんは早速明日からオリエンテーション合宿を皮切りに学校生活が始まります。隣人を自分のように愛する第一歩は自分から友達になることです。まずは新しいクラスメイト全員と自分から友達になってください。そして自分ならこうしてほしいと思うことを、見返りを期待せず友達にしてあげてください。皆さんも経験があると思いますが、このように誰かのためにいいことができた時、たとえ感謝されなくても本当の幸せを感じます。これが隣人愛です。そしてこれに留まらないのが隣人愛の奥深さです。私たちには誰しも馬が合わない人、理解できない人がいて、えてしてそんな人を無視したり、怒りや苛立ちをぶつけがちですが、それをグッと我慢して優しくその人を受け止める。これこそが、より深い隣人愛なのです。
実は今年度は皆さんだけでなく、全校生に隣人愛を一層深め誰に対しても自分から友となることを勧めております。そのため今年度の学校目標は聖書から選び「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人に」としております。というのも、これは自分が本当に人を友として愛せているかどうかがよくわかる言葉だからです。例えば、目の前に喜んでいる人がいるとしましょう。私たちがその人に「すごいね、よかったね。」と言って一緒に喜んでいたならば私たちは間違いなくその人の友です。しかし、その人を見て「チェ」と舌打ちして妬んだり、不愉快に思っていたら友と言えるでしょうか。ましてや、その人の喜びに無関心であるなら友とは言えません。愛の反対は無関心だからです。
同様に、目の前に悲しみくやしさで涙を流している人がいるとしましょう。私たちがその人の辛さを我がことように感じて心を痛め、ともに涙を流していたならば私たちはその人の友です。しかし、こんなことあるかもしれませんね。実は私たちがその人を傷つけ泣かせていたり、その涙を見て「ざまあみろ」と嘲笑っていることが。さらに目の前の悲しんでいる人に無関心で何も感じないならどうでしょう。いずれも友ではありません。このように自分が友として人を愛しているかどうかがこの言葉からわかるのです。そして、ここからが大事な点です。喜びも悲しみも互いに分かち合える友が増えれば増えるほど私たちは幸せです。逆に自分の喜びを喜んでもらえない。自分の悲しみをわかってもらえない。それどころか傷口に塩を塗るような人がいる。この時は、私たちだけでなく、その塩を塗る人さえも心に平安がなく、誰も幸せではありません。喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人になる。これこそが何よりもみんなに幸せをもたらすのです。
さあ82期の皆さん、希望に満ち溢れた6年間がいよいよ始まります。早速今日自分からクラスメイトの友達になってみてください。そして自分ならこうしてほしいと思うことを見返りを期待せず友達にしてあげましょう。皆さんが「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣く人に」なり、やがて6年後には「より大いなるものを知り、他者に奉仕し、世界への懸け橋となるリーダー」となることを切に願って、ご入学に当たっての歓迎の言葉とさせていただきます。