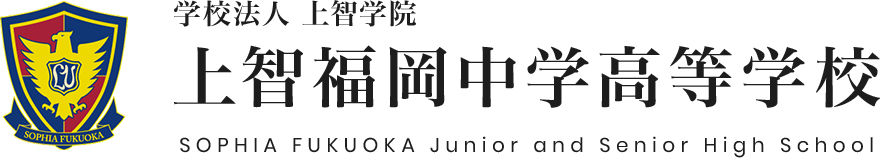2学期の期末考査も終わり、長かった今学期も終盤を迎えています。
思索の時間も再開されましたので、今回は放送の内容を公開しようと思います。
信仰心について
みなさんは、死後私達に訪れることや生まれるずっとずっと前のことなど、絶対にわからないことをあれこれと考えてしまい眠れない、というような夜を過ごしたことがあるでしょうか。
神による天地創造や、天の国や死後のこと、皆さんの手元にある聖書には私達の漠然とした不安に関することが書いてあります。また、このようにしたほうが良い、こんな行動はよくない、というようなことが述べられるたとえ話もいくつか思い出せると思います。それらの話を心から信じることができるならば、このよくわからない不安に「答え」を出してくれるのではないかと思ったことがある人もいるのではないでしょうか。
聖書にはイエスが起こした数々の奇跡が記録されています。みなさんもご存知のように、イエスは病気を治したり、自然の力を操ったりします。いずれも私たちの周りでは起こり得るとは思えない、まさしく驚くべき奇跡ばかりです。このようなことに対して、「奇跡はあったのだと信じなさい」と言われても、疑問は増えるばかりです。不思議なことを信仰の力で理解したことにするのは少し乱暴に感じます。
ここでひとつ、私達が毎日唱える言葉について考えてみたいと思います。
私達はご飯を食べる前に「いただきます」をします。日本の文化の一つとして、しばしばとりあげられる「いただきます」ですが、毎回食材や用意してくれた人へ思いを馳せ、強く祈っているという人はそう多くはないのではないでしょうか。とはいえ、わたしたちは誰に見られていなくても当たり前に「いただきます」をします。なかには、「いただきます」を言わない人に対して不快感を抱く人さえいます。これはある種、日本人の信じているもののひとつとも言えるのではないでしょうか。
では、この信仰によって私達が得る「答え」とは何なのでしょう。「いただきます」の意味については諸説あるようですが、そのなかのひとつに神への感謝や食材の命への感謝を表しているという説があります。何かから食べ物をいただく、という考え方を持ったとき、そこには疑問が浮かび上がってきます。
私達は一体何から、食べ物をいただいていると言っているのだろう?誰に対して言う必要があるのだろう?なぜもらうではなくいただくなのだろう?なぜ食べるときにだけこのような感謝を述べるのだろう?
何かを信じることで答えが見えてくると思いきや、無意識に行っているあいさつでさえ実は多くの問いを生むものであるようです。
信じる心について考えるとき、私にはよく思い出すものがあります。それは、フィリピンにあるとある教会です。この教会は天井がとても低く、教会内のドアをくぐるときには、身をかがめてくぐらなければ隣の部屋へ行くことができません。なぜこのような造りになっているのでしょう。それは、この教会の半分が灰に埋まっているからなのです。
サン・ギレルモ・パリッシュ・チャーチという教会は1576年に建設されました。その後、1880年に地震によって倒壊しますが、6年後に再建されています。そして、1991年、近隣にあるピナツボ山が大噴火を起こしました。事前に噴火の予兆があったため、多くの人が避難していたそうですが、それでも被害は大きく、1000人以上の人が火砕流の犠牲になり、この噴火は20世紀で2番めに大きな噴火とされました。現在でも火山灰の下に犠牲者が眠っているそうです。さて、多数の犠牲者が出た麓の町のこの教会はどうなったかというと、教会のおよそ半分、高さ12メートル分が火山灰に埋まってしまいました。高さ12メートルというと建物の4階相当の高さです。扉は火山灰に埋まり、窓が扉のようになりました。それでも、人々は火山灰の中から祭壇や彫刻を発掘し、灰の上に新たに床をつくり、窓の飾り格子を外して扉に変え、その場所での祈りを続けることを選びました。地震と火砕流の2度の被害を受けても、その場所に形をとどめていることにはまさしく現地の人々の信仰の強さが感じられます。自分たちの生活も立て直さなければならなかったでしょうから、なおさら大変だったことだろうと思います。今では、街の人々の祈りの場であるだけではなく、多くの観光客が訪れる場所となりました。困難に屈せず続いてきた信仰に対しての尊さがこの場所の観光地としての魅力のひとつなのではないでしょうか。
今日は信じることについて考えてきました。私達は何かを信じることによってすぐに答えを得ることは難しく、むしろ、問いを得ていくのだろうと思います。そして、信仰の尊さは続けていくことのなかで表れることがあるようです。漠然とした不安に対する答えはなかなか見つかるものではないでしょう。しかし、問いは答えへの道標になることは確かです。
それはまさしく、聖書に書いてあるとおりです。新約聖書 コリント人への手紙第一 2章9節に次のような言葉があります。
「目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。
神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、みなそうである。」
人が目で見たこともなく、耳で聞いたこともなく、心に思い浮かんだ事のない事を神様は備えて下さるというのですから、聖書を読んで難しく思うのも不思議ありません。
疑問を持ち、自分に問い続けること。その繰り返しの中でいつか聖書に書いてある言葉も理解できるかもしれないと、信じて読む時間を積み重ねていきたいものですね。